
「愛」それは永遠のテーマ。
愛とはいったい何を指すのでしょう。
どうすれば相手は自分を好きになってくれるのでしょう。
専門家の意見も交えて書いてみます。
相手とイイ関係で居続けたいなら愛をもって接することです
人って「自分を受け入れる人間」を好きになるものですよね。
たとえば、
- 他の人がふつうに出来ることがふつうに出来なくても、同じ様に接してくれる
- 「作業服に軽トラ」の出で立ちで誰かをむかえに行っても、普段と変わらずの接し方
- ”金髪にV系の40歳を過ぎたふつうのおっさん”とでもランチに行ってくれる
本人にとってこの状が「普通なこと」だと思う人もいれば、分かっていても「仕方なく、そうしている」人もいます。
どっちにしても嬉しいことですよね。だって自分そのまんまを受け入れるのですから。
そこで「愛とは何か?」について『「普通がいい」という病気』の著書から愛についての言葉を引用してみます。
愛とは、相手(対象)が相手らしく幸せになることを喜ぶ気持ちである。
欲望とは、相手(対象)がこちらの思い通りになることを強要する気もちである。
by 泉谷閑示
なるほど、深いお言葉です。(;´Д`)
自分の都合など考えないし、その相手が望む方向に進んでいることが好きだし、応援したいとさえ考えるものだとわたしは受け取りました。
もしかしたらそれは「その相手のイイ部分を見えいる」からではないでしょうか。
- 仕事が遅くても、謙虚で親切、競争心がないところかも知れない
- 忙しくても要件を優先して直ぐに来てくれることかも知れない
- 自分が気に入いる服を着てワクワクしている相手の姿が好きなのかも知れない
つまり、自分にとってその相手がどうなのか?ではなく、その相手のネガティブな部分(自分・世間・そのときの時流)に合わなくても別にイイのです。
逆にいえば、その相手が望んでもいないのに、無理して自分に合わせていることが心苦しい、とも考えています。
その相手がイイと思っているなら、大事にしたいし、悪いと考えている部分、丸ごと愛おしいのです。
なので「その相手が相手らしくして幸せでいてくれればいい」それが著者がいう愛なのでしょう。わたしもこの言葉に同感です。
まずは自分ルール(価値観)を少しゆるくしてみる
とはいっても、中々実践するのは難しかったりもします。
わたし自身、小学生当時、授業参観に父親には来てほしくはありませんでした。
なぜなら同級生の親よりも一回り上の年齢で、糖尿病もあり、実年齢よりも老けて見えるし、他人に流されないタイプの頑固人だったからです。
「もしかしておじいちゃんなの?」ってクラスメイトに聞かれたこともあるし、「今日は大人しく普通にしていてくれるのか・・」いつもヒヤヒヤ、ハラハラしてました。
人は少なからず「自分にとって理想的な状態」という願望を持っているものですよね。
もしその願望に反することをされた(されなかった)ら、どう思うのでしょう。
前章の内容に照らし合わせると、
- 定時退社したいのに、その足を引っ張られる。同じ給料なのに割に合わない
- 自分をセレブに見せたいから高級車に乗って来てほしい
- 奇抜な服装ではなく「父親らしい格好」でアットホームを演出したい
と考えるでしょう。
なぜなら、他人のトバッチリを受けるのはゴメンだし、ライバルの友人に差をつけて優越感になりたいし、変な噂をたてられることを恐れるから。
自分が大事だし、他人の目が気になるなどの自分ルールに反するからです。
それにプラスして、
- これはふつうな状態なのか
- 自分は周りと比べてどうなのか
- 自分は被害者になってはいないだろうか
なども吟味して「自分にとってメリットなのか」の立ち位置で他人と関わろうとするからでもある。
自分の都合で相手を計るのが願望だといえるでしょう。
そんな中、ふつうの人が欠点だと考える要素を気にせず、逆に「イイところ」だと思ってくれたらどお思うのでしょう。
きっと、良い人間関係で居続けられるのではないでしょうか。
いきなり、心底、自分ルールを変えるのは難しいものです。
まずは自分の許せる範囲を少しづつ広げていくしかないと思います。
気をつけるべきことがある
「これはあなたのためなのよ!あなたのために言っているのよ!」よく聞く言葉があります。
だがしかし、この言葉の裏には「愛という名の暴力」が隠されています。
気をつけるべきことはたくさんありますが、その中の1つを著書の中から引用します。
「愛」に偽装された欲望ほど、子どもを歪めるものはありません。むしろ悪意の方がまだ罪が軽いくらいです。なぜなら、自分に向けられた悪意に対して、人は拒絶や反発をする余地がある。
しかし、「良かれと思って」と相手の善意によって自分に向けられたものについては、拒絶も反発もしづらいものです。P147
たしかに言う通り。
新築祝いに絵画を送られても正直、困ります。自分の趣味じゃないし、自分だけが住む家でもありません。
「捨てるわけにもいかず、飾りたくもない」という人もいました。
とはいえ、もし絵画をくださった相手が家に来た時も気まずいですよね。
これは大変苦痛です。
この様な人を著者は「愛と欲望の区別がつかない人」といっています。
ちょっと手厳しいお言葉ですが真実ではないでしょうか?
この様な状況で相手の心を追い詰めてないか、自問自答することも必要なのですね。
でも、思いやりが根底にあればそれは遅かれ早かれ相手に伝わるものです。
なぜなら長期的になれば、人の本心を見抜けない人間などいないからです。
・
例えばバレンタインに手作りチョコを渡すイベントがあります。
この考え方になれば、
■いただく方は
- 形や味は関係ない。くれた人の気持ちが大事
- 好き嫌い(勘違いされる)ではなく、お返しをしてあげる
■渡す方は
- 甘い物が好きなのか
- その状況で渡して迷惑にならないか
- そこに自分の身勝手はふくまれないか
当たり前のことを書きましたが、その当たり前を実践してこそいい関係が気づけるのではないでしょうか。
おわりに
そんな偉そうに書きましたが、わたし自身、直す部分はたくさんあります。
トライアル・アンド・エラー。失敗してまた挑戦し、試行錯誤して、昨日よりも一歩でも良い状態なれたらイイですよね。(*^_^*)
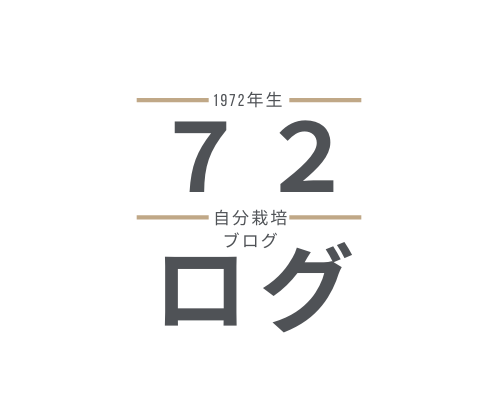


もっと探してみる